アクセスが激減した。順位が落ちた。
どこを直せばいいのかわからない。
いや、もはやどうすればいいのかもわからない!思考停止状態…
そんな状況であろうとも、「お問い合わせ」「購入」に繋げないとやばい!
どんな状況であろうとも、これだけは声を大にして伝える必要があります!
それは・・・
定期的な「更新」は必ず行い、そして「認知度」を向上させる施策をすることです!
現状、これが最適解であり、解決策になります!
Googleのコアアップデート
Googleのコアアップデートが実施されるたび、多くのサイト運営者やライターが戸惑い、焦り、そして疲弊していきます。これまで更新して積み上げてきたウェブサイト、そして記事が突然「評価されなくなる」という事態に、モチベーションごと奪われてしまうウェブ担当者も少なくありません。
では、この不定期に「評価基準が変わる時代」に、どう向き合えばいいのでしょうか?
今回の内容は、単なる「順位回復のテクニック」ではなく、コアアップデートに左右されにくいウェブサイト構築のための本質的な視点。つまり「中長期で信頼され、結果を出せるサイト運営とは何か?」を、実践的に解説していきます。
不定期に行われるアップデートに怯えたり、アップデートに振り回されるのではなく、そしてアップデートを味方につけるために。
ここからは御社のウェブサイトにしかできない価値づくりを始めていきましょう。
記事を「更新」していますか?これは絶対に必要なこと
Googleのコアアップデートを受けたとき、確認すべき1つは「過去に上位表示されていた記事の鮮度が落ちていないか?」という視点です。SEOにおける「記事の更新」は、単なる追記ではなく、「情報の正確性」「網羅性」「検索意図とのズレ修正」までを含んだ総合的なリフレッシュ作業を意味します。
特に、検索ボリュームの大きなYMYL系ジャンル(健康・お金・法律・人生に影響を及ぼすテーマ)は、古い情報が放置されているだけで順位が大きく下がる傾向にあります。読者の役に立つかどうか以前に、「古いまま」というだけで信頼性を欠くと判断されてしまうのです。
これは、YMYL系ジャンルの記事が圧倒的に多いことが挙げられ、つまり競争が極度に激しいジャンルを意味し、結果的に圧倒的にライバルが多いことを意味します。
たとえば、数年前に書いた「インスタ集客の方法」や「おすすめのクレジットカード」などは、アルゴリズムや市場環境の変化によって情報が陳腐化しやすく、手を加えていなければほぼ確実に評価が下がります。
また、Googleは「更新されたかどうか」だけでなく、「何がどれだけ更新されたのか」も見ています。単なる日付の上書きや、1〜2行の加筆では評価されないケースも多く、全体の構成見直しやビジュアルの差し替え、事例の刷新など「本気の更新」が必要とされます。
理想は、コアアップデートが起きる前に、自分のサイトで検索上位にいる記事・トラフィックのある記事をスプレッドシート等でリストアップし、「更新予定」「更新履歴」「次回確認日」などを管理しておくこと。運営歴の長いメディアほど「資産の劣化管理」が肝になります。
しかし、ここまでの施策ができる企業や個人はそう多くはありません。ものすごいリソース「時間・資金・技術・継続」が必要です。しかも確実な結果が保証されません。あくまでも最善を尽くすというものです。これで上位アクセスの可能性を高めます。
この施策によって、気になるのは、どれだけの費用対効果が見込めるかではないでしょうか?
企業の多くは、いまだにウェブサイトに関連する経費を重要視できないでいます。なぜでしょう?それはウェブサイトの存在を軽視しているからほかなりません。この軽視を重要視に変換することができないでいるのです。つまり経営者の思考中域に「改革の乗り遅れ現象」が発生しているわけです。
何度もお伝えしていますが、コアアップデートで明暗が分かれる分岐点のひとつが、「日頃から記事を更新していたかどうか」です。書いて終わりの運営スタイルは、アップデートのたびに順位が下がるのは当然です。
そして、さらに危惧しなくてはならない点は、新たな競合ライバルが新たなウェブサイトを立ち上げていることです。
それでも、まだ御社はウェブサイトの存在を軽視し続けますか?
現在、先見の明をもった「改革思考の経営者」が、ウェブサイトの存在に対して重要視しています。つまりウェブサイトの施策に対する経費の重要性を理解したわけです。近年ウェブサイトの専門スタッフの雇用が著しく増加しているようです。
アップデートに振り回される心境
Googleのコアアップデートが実施されるたびに、「アクセスが激減した」「順位が暴落した」といった声が飛び交います。実際、それまで検索上位にいた記事が突然10位圏外へ落ちることも珍しくありません。こうした「振り回される現象」はなぜ起こるのでしょうか?
ひとつには、そもそも「安定すること」が前提になっていたこと自体が誤解だという問題があります
よくよく考えてもみればわかることなのですが、Googleの検索順位は「変動するもの」であり、よりよい情報が生まれれば入れ替えられて当然です。更新もせず、改善もせず、ただ「維持されるもの」と期待し、安心している状態では、変化に対応できずに取り残されてしまうのは明白ではないでしょうか。
もうひとつの理由は、小手先のSEO施策に依存しすぎているサイト運営にあります。
キーワードの詰め込み、記事のテンプレ量産、外注による中身の薄い記事、AI生成だけの記事構成…。これらの施策は、アルゴリズムの「穴」を突いて一時的に上位を取れることもありますが、Googleがアップデートを通じて「真に価値のある情報かどうか」を見直すたびに、淘汰されてしまいます。
つまり「攻略だけに注視していては本質的な目的を見失う」という状況を招くわけです。
たとえば、「競合より少し多く文字数を書く」「共起語を散りばめる」「サジェストを全て拾ってH2にする」といった施策は、かつては機能していたかもしれませんが、今はむしろ機械的、不自然と判断されることもあります。これらのテクニックは、アルゴリズムの変化に弱く、結果的に「頼れる軸」にはなりにくいわけです。
つまり、アップデートで振り回されるのは、「Googleの評価基準を本質的に理解せず、運営を機械的な施策に依存してきた結果」であることが多いのです。
運営者が本当に考えるべきことは、Googleが何を見ようとしているのか、その意図を読み取る力を持つことです。そうすれば、アルゴリズムが多少変わっても「本質的に価値のある情報は上がるはず」という視点が持てるようになり、むしろアップデートを歓迎できるようになります。
そして、もっと本質的なことを言ってしまえば
ユーザーが何を求めているのか。そして、何を伝えたいのか。これらを意識することです。
Googleは何を評価しているのか?アップデートの意図を読む
コアアップデートが繰り返される中で、もっとも重要な姿勢は「評価軸が変わった」というよりは、「精度が上がった」と捉えることも重要です。
Googleは一貫して、「ユーザーにとって役立つ情報を、適切な順番で届ける」ことを目的としており、その大方針は1ミリも変わっていないと言えるからです。
それもそのはずで、ユーザーに役立たない情報を、上位表示させる方が無理があるからです。
では、何が「より評価されるようになった」のか?ここでよく語られるのが、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)という考え方です。これは、Googleの品質評価ガイドラインに基づいた根本的な評価基準であり、特にYMYL(お金・健康・法律などの人生に関わるテーマ)では強く作用します。
具体的には、次のような要素が見られています。
これらは、検索順位だけでなく、読者の信頼や満足度にも直結します。そしてコアアップデートは、このE-E-A-Tの各項目を判断する「アルゴリズムの精度」を強化する動きに過ぎないのです。
さらに最近では、「Helpful Content(役立つ内容かどうか)」という概念も重視されています。これは、検索エンジン向けではなく読者のために作られたコンテンツかどうかを重く見るという評価方針で、見せかけのSEO記事やAI量産記事を排除するためのアップデートでもあります。
つまり、Googleのコアアップデートでは、本物かどうかを見定めようとしているのです。しかし、これを人力で行うのは絶対に無理です。なにせ現在のウェブサイトは世界中で10億サイト以上が存在するからです。ですからこれをプログラムで管理と精査をするわけです。このプログラムによる仕組みは、古くから数学やコンピュータ分野で使われてきた言葉を用いて『アルゴリズム』と呼ばれています。Googleも検索順位を決定する仕組みを『検索アルゴリズム』と呼んでいるわけです。
たとえば、「〜とは?」の定義だけで終わる記事、「知識ゼロでもOK」と言いながら表面的な解説しかしていない記事、「すべての疑問を解決します」と言いながらテンプレ化された中身の薄い記事…。こうした「自称親切」なページは、今後ますます上位に残れなくなっていきます。
アップデートに影響されないウェブ・コンテンツを作るためには、「Googleがどう見ているか」を知るだけでなく、「読者にどう届いているか」を自問する視点を忘れてはなりません。検索流入はアルゴリズムで生まれますが、評価の本質は人間の納得感にあることは間違いありません。
読者は「探していない」時にも流入してくる
SEOというと、「検索した人にどう見つけてもらうか」という視点に偏りがちですが、実際の流入経路はもっと多様です。とくに2020年代以降、読者は「何かを探しているとき」だけでなく、「探していないとき」にも記事やコンテンツと出会うことがあります。
たとえば、以下のような経路が増えています。
こうした経路の共通点は、「読者が能動的に検索していない」という点です。つまり、「問いを持っていない状態」の読者に、ふと届けられる可能性があるということ。ここで重要になるのは、記事のタイトルやサムネイル、冒頭の一文が「読んでみたい」と思わせる魅力的な一文かという視点です。
検索ユーザーには「答え」や「説明」を与える構成が求められますが、探していない読者には「視点」や「共感」「意外性」「刺さる言い回し」が刺さります。単なる情報ではなく、「今の自分に必要だった」と感じさせる「気づき型コンテンツ」が強いわけです。
つまり、歩いていて「ふと立ち止まってみたくなる」という状況です。
また、Google自体も「Discover」や「おすすめ記事枠」を強化しており、これは検索ではなく「潜在的な関心」に基づいて表示される仕組みです。ここに掲載されるには、クリック率(タイトル・サムネ)+滞在時間+ページ品質が鍵になります。
つまり、検索からの流入だけを想定してコンテンツを設計していると、現代の情報流通の大半を見落としていることになります。SEO対策とは「検索ワードに最適化すること」だけでなく、「発見され方を設計すること」でもあると捉えるべきです。
つまり、流入経路を増やすことが王道になってくるというわけです。
流入の全体像を見渡し、「探されなくても届く」ウェブコンテンツを育てていくことが、アップデートにも強いサイト作りの土台になるというわけです。
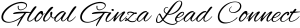



コメントをお寄せください コメントをいただけるとこのうえない喜びです♪