前編では、Googleコアアップデートに振り回される理由と、アルゴリズムの本質について整理しました。検索順位の変動は避けられず、安定を期待するほど苦しくなる。その現実を受け入れたうえで重要なのは、「依存しない仕組み」を持つことです。
では、アクセスの大半をGoogle検索に頼ってきたサイトは、どうやって脱却できるのか。ここからは、検索に依存しすぎず、長期的に成果を残せるウェブコンテンツの運営の実践策について解説していきます。
ただし、誤解してほしくないのは、あくまでも「検索の流入」は意識する必要があります。そのうえで、同時に対策をしていく意識を持つ必要性をこのページでは説明しています。
まず最初に直面するのは、多くの運営者が抱える根本的な不安…「検索されなくなったら終わりではないか?」という恐怖です。この恐怖をどう乗り越え、どんな視点を持てばよいのか。最初のステップとして、ここから掘り下げていきましょう。
「検索されなくなったら終わり」という恐怖との対処法
アクセスのほとんどを、Google検索に依存していた!
こういうウェブサイトはかなり多いのではないでしょうか?当社が運営しているウェブサイトもそうでした。
アクセスのほとんどをGoogle検索に依存していると、コアアップデートのたびにサイト運営者は「次は自分の番かもしれない」という不安に襲われるという声が多いことがわかっています。
アクセスが減る=売上が落ちる=存続が危うい
この負のスパイラルから抜け出せないまま、多くの個人ブログや小規模メディアが淘汰されてきました。
余談ですが、これは精神論の類のお話になってしまいますが、精神的な重圧によって、それまで良好だった取り組みが一気に調子を崩してしまうということもあります。加えて迷いによって、「良質なコンテンツ(記事)を改悪してしまった…」なんてこともあります。一方で、重圧によって逆にモチベーションを高める人もいます。
しかし今や、この「検索されなくなったら終わり」という考え方自体がリスクです。
検索流入をメインに設計していたとしても、それだけに依存している状態はビジネスとして非常に脆弱です。では、どのようにしてその依存状態を脱却できるのでしょうか?
まず第一に考えるべきは、「検索以外の経路」で繰り返し接触できる仕組みを持つことです。たとえば、
つまり、「一度でも価値を感じた読者が、検索なしでも再訪問できる状態」をつくることが目的です。
また、記事の役割も再定義する必要があります。検索上位を取るためだけではなく、「資料の入口」「サービス説明の導線」「商品比較のサポート」など、サイト内での機能別に設計された記事があると、検索順位の上下とは別の軸で機能し続ける「情報資産」になります。
つまりブックマークをして、再度別の機会に訪れたくなるウェブサイトにすることです。そのために定期的な「更新」は必須になってきます。
さらに重要なのが、「集客記事」「ブランド記事」「収益記事」のバランスを取ることです。たとえば、
この3つを分離して設計すれば、仮に検索順位が落ちても、ブランド記事での認知が残り、収益記事での成約が維持される…、というように、検索アルゴリズムの影響を相対化できます。
「検索で来る読者」だけでなく、「検索しなくてもつながる読者」を育てていく。
これが今後のコンテンツ運営における、もっとも堅実なリスク分散策です。
もっと、わかりやすく言うと、URLを掲載した名刺を渡すことです。このアクションの積み重ねがアクセスアップに繋がります。仮にアクセスが50でも、50人から購入されればよいだけです。そして1人が1億円の商品を購入してくれたとすれば50億円です。なんだか簡単なように思えてきませんか?
アクセスが減っても「信頼」は残るウェブサイトを育てる
1つ言えることは、コアアップデートでアクセスが落ちたとしても、それが「サイトの価値が下がった」こととイコールであるとは限らないということを知っておく必要があります。
この点を誤った見解を持つことで、慌てふためき、自暴自棄になるケースもあります。冷静に情報を集めて、被害を最小限にしながら、できる対策をおこなうことが大切です。できる限り1人で悩むことは避けてください。あなたは1人ではありません。
ですが、誰かを頼ると資金がかかります。
この時期を乗り切るために、資金はかかるかもしれません。
いずれにせよ、数字が減っても「信頼」が残っているウェブサイトかどうかが、運営の分水嶺(物事の方向性が決まる分かれ目)になります。
たとえば、以下のようなケースです。
これらはすべて、「Googleの評価」とは別軸で積み上がる「信頼の証拠」です。そして、この「人からの評価」があるメディアほど、長期的に見て検索順位も復活しやすいという傾向があるのは確かです。
信頼の残るメディアに共通しているのは、以下のような特徴です。
こうした蓄積があるメディアは、仮にアクセス数が一時的に落ちても、「あそこに行けば信頼できる情報がある」という読者側の印象が残るため、再評価される確率も高くなります。
そうなるためには、一貫して継続更新が求められます。
まさに、雨のときも、雪のときも、嵐のときも、涙が止まらない日も…続けるのです。
また、アクセスに固執しすぎると、必要以上に煽り系タイトルや無理なCV導線を増やしてしまい、読者との信頼関係を逆に損なうリスクがあります。アクセス数よりも、「どんな人が、どういう意図で、どう読んでいるか」という「読まれ方の質」を重視する意識も、信頼を守る姿勢として大切です。
数字が下がったときこそ、焦って短期的な施策を取らず、「信頼を残す記事」を丁寧に育ててきたかどうかが、今後の分岐点になります。
結局、勝ち残るのは「人間にしか書けない記事」
AI記事生成ツールの進化により、誰でも簡単に数万文字の記事を量産できる時代になりました。実際、多くのウェブサイトでAIを活用したコンテンツが増え、見た目は整っていて一見わかりやすい記事があふれています。しかし、コアアップデートで評価され続けているのは、「人間の知恵」や「体験の熱量」が感じられる記事です。
たとえば、以下のような要素は、AIにはまだ出せません。
Googleがコアアップデートを通じて厳しくチェックしているのは、「この内容はAIでも生成できるのでは?」という部分です。逆にいえば、「AIでは再現しにくい文脈や人間的な判断・経験・思考」を感じさせる内容があるかどうかが、評価されるか否かの分かれ目になります。
つまり、今後は単なる情報の整理や構造化だけでは不十分です。そのテーマを語るに値する立場かどうか、語る意味があるかどうか、語りの中に血が通っているかどうかが問われます。
このAI時代に強い記事は、「自分にしか書けない記事」を持っているウェブサイトです。それは専門家の視点であったり、現場での実体験であったり、失敗談であったり、顧客のリアルな声であったり…。それぞれの立場や経験によって、文章の「厚み」が変わってくるのです。
たとえば同じ「不動産投資のリスク」というテーマでも、
この違いは一目瞭然です。前者は薄く、後者は「人間的で引き込まれる」のです。
Googleが進化すればするほど、機械的な量産物は淘汰され、文脈と背景を持つ「人間の書いた記事」が残っていくという流れは変わりません。
AIが生成した記事に「魂」を吹き込むことができるのは「人間」だけというわけです。少なくとも今のところは…。
「書き手の存在」が明確か?
コアアップデート後に大きく評価が下がったサイトの多くに共通するのが、「誰が書いているか」が不明確なまま情報が並べられているという点です。どれだけ正しいことを書いていても、読者もGoogleも「発信者の素性が見えない」ものを信頼することはできません。
これは、E-E-A-Tの中でも 「E(経験)」と「T(信頼性)」を構成する重要要素です。
Googleは、情報の正確さだけでなく、「この人が語る意味はあるのか?」「読者はこの人を信じる根拠があるのか?」という視点を常に見ています。とくに医療・金融・人間関係・転職など、人生に関わるジャンルでは、「顔の見えない発信者」や「背景が不明な記事」は強く減点される傾向があります。
では、どのように「書き手の存在」を明確にすべきか?ポイントは以下の通りです。
このような取り組みは、SEOのテクニックではなく、「読者との信頼関係を築くための基礎」となります。
とくに近年は、ChatGPTなどのAIを活用した「誰でも書ける風のコンテンツ」が急増しており、Google側も「書き手の信頼性」をより重視するようになっています。AIが生成した記事は、「誰が書いたか」の説明責任を果たせないため、評価対象になりにくくなっているのです。
逆に言えば、実在する個人・団体が責任を持って運営し、「この人なら信用できそう」と思わせられる発信者が書いているサイトは、アップデートの影響を受けづらくなります。
今後のSEOでは、「質の高い記事か?」の前に、「誰がその内容を語っているのか?」という信頼設計が必須条件になります。「内容」だけで勝負する時代は、すでに終わっていると言えそうです。SNSの世界でも同様で、同じ内容の発信をしているのに、あの人が発信しているだけで、大量の「イイね」を獲得しています…これが現実です。
1記事単体ではなく「サイト全体の思想」が問われる
かつてのSEOの施策としては、「1記事ごとにキーワードを狙う」というスタイルが主流でした。特定の検索語に対して個別に最適化された記事を量産し、いかに広く網を張るか。それが上位表示の勝敗を分けていた時代です。しかし現在、Googleは単一ページの良し悪しだけではなく、「そのページがどんなサイトの一部か」まで含めて評価しています。
これは、「サイトの世界観」「情報の一貫性」「テーマの深さ」など、「思想レベルの設計」が検索順位に影響を与える時代になったということです。
たとえば、「副業の始め方」という記事があったとしても──
これは、Googleがユーザー満足度の観点から「そのサイトに期待できる専門性は何か?」を見ている証拠です。そして、その「専門性」とは単なる情報量ではなく、「このサイトが掲げている価値観や編集方針がぶれていないか?」という信頼にもつながります。
つまり今後は、「どんな記事を書くか」以上に、「どんなメディアをつくっているか」が問われる時代です。
たとえ1本1本のコンテンツが高品質でも、サイト全体の統一感や編集思想が希薄であれば、「情報の寄せ集め」とみなされ、検索順位が伸び悩むことは珍しくありません。
逆に、「強い思想」を持ったサイトは、1記事単体で狙っていないキーワードでも評価されることがあります。これは、Googleが「このジャンルならこのサイトだろう」と判断している証拠です。
長期的に見て、アルゴリズムに左右されない強いメディアを育てたいなら、記事の量や数値の前に、まず「思想」の設計が必要不可欠なのです。
SEO対策=Google対策ではない
多くのウェブ担当者、運営者が、「SEO=Google対策」と捉えていたりするのではないでしょうか。
確かに現実として、検索エンジンのシェアを見ればGoogleが圧倒的であり、検索順位を上げたいならGoogleに最適化するのは当然です。しかし、その視点だけに縛られると、コンテンツ本来の目的がブレてしまうというリスクを生じさせてしまうケースがあります。
そもそも、SEOとは「Search Engine Optimization=検索エンジン最適化」ですが、Googleに対する「裏技」を駆使することではありません。本来の目的は、検索を通じてユーザーと出会い、最適な情報や価値を届けることです。つまり、「読者視点」での最適化こそが本質であり、Googleはあくまでその中継地点にすぎません。
たとえば、次のような現象はよく見られたりします。
これらは、Googleという「評価者」にばかり最適化しすぎて、本来届けるべき「読者」を置き去りにしている典型例です。
つまり、Googleのアルゴリズムはまだ未完成なのです。この未完成の状態のアルゴリズムに従わないとならない立場であることが、悲劇をもたらしていることは確かです。
逆に、「Googleには評価されていないが、読者の反応がすこぶる良い記事」もあります。こうした記事がシェアされ、引用され、再訪問されることで、結果として自然な被リンクや指名検索につながり、後から検索順位も上がってくる──という流れは今も普通に存在しています。
つまり、Googleはあくまで「読者の満足度を計る手段」であって、目的ではない…と言えそうです。目指すべきは「Googleのために書いた記事」ではなく、「読者に刺さる記事を、Googleが自然と評価してくれる」状態と言えそうですね。
また、今後の検索行動はGoogleだけに留まりません。
ChatGPTやPerplexityのようなAI検索、TikTok検索、X検索、YouTube検索など「検索される場所」自体が多様化してきています。もはやSEOは「Googleだけの話」ではなく、あらゆる出会い方を想定した「情報の届け方の最適化」と捉える必要があります。
そのためには、目先の検索順位に一喜一憂するよりも、「読者との関係性」「価値ある記事の設計」「届けたい相手の明確化」といった、「マーケティングと編集の力」がますます問われる時代になってきているのです。
そして、数で勝負という姿勢にも注目しなければなりません。今や複数のSNSから同時に発信している成功している人や企業が多くあるのですから。
AI記事生成とどう共存するか
ChatGPTをはじめとするAIライティングツールの進化によって、「誰でも簡単に記事が書ける」時代が到来しました。実際、ブログ・企業サイト・まとめ系メディアの多くが、記事制作にAIを導入しています。では、こうした時代において人間のライターや運営者は、どうやって生き残るべきなのでしょうか?
答えはシンプルです。AIと競争するのではなく、「共存」し、役割分担を明確にすることです。
AIは非常に優秀な補助ツールです。
構成案のたたき台、テンプレ文章、要点の整理、FAQの生成など、ルーティン業務や汎用的な表現に関してはスピードと正確性があります。しかし、以下のような領域では、いまだに人間の力が不可欠です。
これらは、ただ情報を並べるだけのAIには出せない「人間の血の通った文章」です。
つまり、AIには「型をつくる」作業を任せ、人間は「意味を吹き込む」役割に集中するべきなのです。たとえば、
- キーワード選定 → AIに候補を出させる
- 見出し案 → AIで複数パターンを生成
- 書き出しの下書き → AIでたたき台を用意
- 文章全体の温度調整・語尾・言葉選び → 人間が担う
- 構成と導線 → 編集者視点で精査する
このように役割を分けることで、効率と質の両立が可能になります。結果として、「AIが生成したとは思えないクオリティだが、スピードは異常に速い」という理想的な記事作成体制が構築できるのです。
また、AI時代のSEOで求められるのは、「見た目が良い記事」ではなく、「本当に読まれて価値がある記事」です。AI記事が増えるほど、「読者の心を動かせる記事」が際立つようになります。
今後は、「AIの波に飲まれたくない」ではなく、「AIで効率化した分、人間にしかできない部分に集中する」ことが勝ち残りの鍵だと思います。
「Googleを信用しすぎること」自体がリスク
多くのウェブサイト運営者が「Googleに評価されるかどうか」を軸にコンテンツ設計や戦略を組んでいます。たしかに検索エンジン経由の流入は、安定性・成約率・成長性の点で優れており、Googleを意識するのは当然です。しかし、Googleに依存しすぎる構造は、それ自体が非常に大きなリスクになります。
なぜなら、Googleは「他社のサービス」であり、自分ではコントロールできないアルゴリズムに命運を握られている状態だからです。
言葉を選ばずに言ってしまえば、生殺与奪の権利を与えてはなりません。
たとえば、
これらはどれも、運営者の努力とは関係なく起きる「外部要因」です。
つまり、どれだけ質の高い記事を積み重ねてきても、Googleのアルゴリズム変更や市場変化によって、1日で集客の仕組みが崩れる可能性があるということです。
このリスクを避けるには、Googleはあくまで「導線のひとつ」として捉え、複数の集客ルートと信頼獲得手段を同時に育てておく必要があります。
たとえば:
また、Googleが求めているのは「Googleに従うサイト」ではなく、「本当に価値あるサイト」が検索で評価されることです。つまり、Googleに媚びずとも、ユーザーに求められていれば、結果的にGoogleが評価するようになるという順番が正解なのです。
「Googleの評価がすべて」ではなく、「Google以外でも評価される状態」を目指すことが大切です。この視点がなければ、アップデートのたびに振り回され、路線変更を繰り返す「消耗型運営」に陥ってしまいます。
もちろん、常にサチコ(サーチコンソール)とにらめっこすること自体を否定するわけではありません。ですが最善を尽くした記事を書いたのなら、あとはその記事に宿った魂に命運を委ねるつもりで、のんびりすることも、また1つの仕事だと思うのです。
まとめ・伝えたいこと
Googleのコアアップデートは、これからも定期的に実施され、内容はさらに精緻化していくことが予想されます。しかし、そのたびにアクセス数に一喜一憂し、場当たり的な対策を講じるだけでは、長期的な成果にはつながりません。
そればかりか心身ともに疲弊します。
本記事でお伝えしてきたように、コアアップデートに強いサイトとは、単にSEOの「テクニック」に長けているサイトではなく、
- 読者との関係性を大切にし
- 情報の鮮度と信頼性を継続的に保ち
- 書き手の存在を明確にし
- AIや検索に依存しすぎず
- メディア全体としての思想を持ち、発信を続けている
こうした、「人間としての運営意図」が通っているウェブサイト・メディアです。
Googleの評価は常に変わっていきます。
検索エンジンの仕組みも、競合の動きも、AIの進化も止まりません。そのなかで唯一、変えられるものがあるとすれば、あなた自身の言葉と視点、そしてメディアとして何を伝えたいかという本質的な軸です。
コアアップデートに勝つのではなく、「アップデートを歓迎できる側」に回るために。
「評価されるコンテンツ」ではなく、「誰かの記憶に残るコンテンツ」を。
その積み重ねこそが、Googleを超えて残る「情報発信資産」となります。
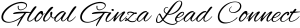





コメントをお寄せください コメントをいただけるとこのうえない喜びです♪