例えば・・・。
もしあなたが、新しいお店を探していて、検索して出てきた情報が「公式サイトしかない」としたらどう感じますか?なんとなく「本当に信頼できるのかな」と不安になることはないでしょうか。
逆に、公式サイトのほかに、業界のポータルサイトや、専門メディアで紹介されていたとしたらどうでしょう。「他でも取り上げられている=信頼できるのかも」という安心感が生まれませんか?
これは、あなたが特別に慎重なわけではなく、多くの人に共通する「心理作用」なのです。人は、誰かにすすめられたり、多くの人に支持されていたりするものに対して、安心して選びやすくなる傾向があるというわけです。実際、これは自然なことです。
これはネットの世界でも同じです。公式サイトの情報だけでなく、「第三者がどのように評価しているか」「ほかの信頼できる場所でも取り上げられているか」が、購買や申込みの決断に大きく影響しているのです。
そして、信憑性、実在性、認知度が信頼に繋がり、安心を担保してくれるというわけです。
これが、あなたのサイトに必要な材料ですし、あなたがこの記事にたどり着いた理由なのです。
- 取引先のホームぺージを検索したとき、専門サイトからの推薦記事を見かけたら安心しませんか?
- たとえば、【ワクワクワッフル】というお店のワッフル専門店のサイトを検索した際に、他のサイトにも記事が掲載されているのを知り、知名度があるんだなと思いませんか?
- ウィンザー効果を自然な流れで活用することが大切です
- 検索に複数の御社、屋号が出ているとユーザーは安心感をいだき公式ホームページを再度見に行きます
- 現在、知名度のない優良企業は多い
- SNSでは人気がなさそうに見えて、美味しい街のパン屋さんってありませんか?問題なのは知名度なのです
- 知名度、認知度を増加させる効果
- なぜ人は「中立の声」を求めるのか?
- BtoB企業こそ「紹介されている事実」が武器になる
- 「自社で発信できないこと」を、第三者は代弁できる
- 専門的な立場からの言葉は、信頼を生む
- 推薦記事は「資産」。SNS投稿との違い
- 自画自賛の記事は滑稽。だから第三者視点の記事が効果を発揮する
- つまり…
取引先のホームぺージを検索したとき、専門サイトからの推薦記事を見かけたら安心しませんか?
ビジネスでも個人でも、Webでの取引前に相手の会社を検索するのは、もはや当たり前になりました
その際、単なる自社運営のホームページだけでなく、別の専門サイトやポータルメディアでもその会社の紹介記事を見かけたら、それだけで「この会社は信頼されているんだな」と思うのが、現在のスタンダードだそうです。
たとえば、Webマーケティングを外注しようとしているときに、検索して出てきた企業の名前が、業界系メディアの記事で複数取り上げられていたら、それだけでかなりの安心感を感じさせるでしょう。逆に、どれだけホームページが綺麗でも「どこにも名前が出てこない」状態では、躊躇する方も多いのです。もちろん業種によってはこういう現象は起こります。
だからこそ、今あなたは「差」をつけるチャンスがあるのです!
これは、BtoBでもBtoCでも同じ傾向であります。ユーザーの不安を払拭するためには、「自社発信だけでない情報」が必要なのです。
つまり当社のサービスを活用することが効果的で、格安である上に永久掲載だから、コストパフォーマスに優れています!そして今すぐお役に立てるのです!
たとえば、【ワクワクワッフル】というお店のワッフル専門店のサイトを検索した際に、他のサイトにも記事が掲載されているのを知り、知名度があるんだなと思いませんか?
仮にあなたが「ワクワクワッフル」という店名のワッフル専門店をネットで見つけたとします。公式サイトを訪れて、美味しそうな写真や丁寧な説明が並んでいたとしても、それだけでは「よし、行こう!」とまでは思えないかもしれません。
でも、Google検索で「ワクワクワッフル」と入力したときに、食べログやレッティ、あるいはグルメ系のまとめサイト、さらにはスイーツ専門ブログなど、複数のページでこのお店が紹介されていたとしたらどうでしょうか?
「え!けっこう人気なんだな」「専門家も評価してるなら、行ってみようかな」そう感じるのが自然なはずです。これは、Web上での「第三者評価」が与える力の一例です。知らないお店でも、「あちこちで取り上げられている」ことで、信頼できるように見えてくるのです。
そして不思議なことに、驚くほど本当に多くの人から信頼される企業やサービスに成長します!是非ご自身で体感してください!
ウィンザー効果を自然な流れで活用することが大切です
心理学で「ウィンザー効果」。
本人からの直接的な情報よりも、第三者からの評価や推薦の方が信頼されやすいという法則です。
たとえば、ある商品が「これはとても良い製品です」と公式がアピールしているだけでは響きませんが、口コミや専門家のレビューで「これ、いいですよ」と語られると、突然その商品が魅力的に感じられるのです。
この心理を理解している企業は、SNSのインフルエンサーとのタイアップ、比較サイトでのレビュー獲得、または業界サイトでの掲載などを積極的に行っています。
つまり「自社ではなく、他者からの推薦」をつくることが、信頼を得るためにとても効果的なのです。
そして、その効果は、同時に「認知度」もあげてくれるのです。
検索に複数の御社、屋号が出ているとユーザーは安心感をいだき公式ホームページを再度見に行きます
ユーザーは商品やサービスに興味を持ったとき、まずは公式サイトを見ます。そこである程度の印象が決まりますが、次に行うのは「検索」です。
「会社名 口コミ」「屋号 評判」「○○(店名) ブログ」などで再検索し、ほかの情報があるかを確認します。
このとき、複数のメディアや個人ブログ、専門サイトなどで自社の名前が出てくると、「あ、ここってちゃんと知られているんだ」とユーザーの信頼が強まります。
そしてもう一度、最初に見た公式ホームページへ戻ってくるのです。今度は「信用した上での再訪問」です。
ここで予約・申込・購入といったアクションが初めて起こります。
つまり、「複数の第三者メディアに登場する」ことは、公式サイトのコンバージョンを高めるうえで極めて重要な仕掛けなのです。
現在、知名度のない優良企業は多い
世の中には、実際にはとても誠実で、良質な商品・サービスを提供しているのに、知名度がないために評価されていない企業が数多く存在します。
あなたの企業やサービスがそうであるかもしれません。
検索しても出てこない、または公式サイトだけで他に情報が見つからない──。そんな企業は、どんなに中身が良くても、お客にとって「未知の存在」でしかありません。
逆に、大手のように広告や広報に力を入れていなくても、信頼される企業には「どこかで見たことがある」という印象を与えるための情報設計がなされているものです。
今は「知られていないだけ」で、不利な立場にいる優良企業こそ、「第三者の紹介」という視点を持つべきなのです。
つまり当社のサービスを活用することが効果的で、格安である上に永久掲載だから、コストパフォーマスに優れています!そして今すぐお役に立てるのです!
SNSでは人気がなさそうに見えて、美味しい街のパン屋さんってありませんか?問題なのは知名度なのです
あなたの街にも、「SNSでは話題になっていないのに、実はめちゃくちゃ美味しいパン屋さん」があるのではないでしょうか?
こうしたお店は、ファンにとっては「秘密にしておきたい名店」かもしれませんが、経営的には「知られていない=集客に苦労する」状況でもあります。
これはパン屋に限らず、美容室、ネイルサロン、学習塾、整体院など、地域密着型のサービス全般に共通する課題なのです。
広告費をかけられない中小事業者ほど、認知度をどう獲得していくかがカギになります。SNSやブログの更新を続けるのも一つの手ですが、なかなか手が回らない現実もあるでしょう。
そんなときこそ、「外部から紹介してもらう仕組み」を活用することで、手間をかけずに知名度アップを図ることができるのです。
知名度、認知度を増加させる効果
繰り返しますが、人は「自分以外の誰かが認めているもの」に安心感を抱きます。
これは真理です。
これは広告でも自作のSNSでもなく、「第三者による紹介」で得られる効果です。
特に、業界ポータルや地域メディア、専門ブログなど、ある程度の信頼性が担保された場で取り上げられると、検索にも強くなりますし、認知度がじわじわと広がっていきます。
そして最終的には「なんとなく名前を知っていた」「あ、前に見たことあるかも」と感じさせることで、購買行動につながるのです。
「知られている」ということ自体が、価値になるわけです。
なぜ人は「中立の声」を求めるのか?
人は本能的に「バイアスのない情報」を探します。
これは心理学でいう「確証バイアス」や「信頼性ヒューリスティック」とも関係しています。たとえば、自分に都合の良い情報だけを信じたがる一方で、その情報が「売り手本人の言葉」であればあるほど、疑ってかかるという心理が働くのです。
「売り込みたいから、良く書いているのだろう」と思われた瞬間、どんなに優れた内容でも、その説得力は大きく損なわれます。逆に、同じ内容であっても、第三者⋯、つまり「中立」の立場の人間が評価・推薦していれば、それは格段に信頼性を持ち始めます。
人間の脳は「自分の判断が間違っていないと裏付けてくれる情報」に安心感を覚えます。中立の声とは、まさにその「裏付け」なのです。誰かの紹介や推薦記事は、情報の正確性を補強する補助線として機能し、読者の行動を一歩前に進める力を持っています。
BtoB企業こそ「紹介されている事実」が武器になる
BtoCではユーザーの感情や話題性が重視されますが、BtoBにおいては「信頼」と「実績」が最重要視されます。企業間取引では、意思決定者が複数いたり、慎重な稟議フローを経て契約が決まるケースが多いため、単なる営業トークだけでは突破できません。
そんなとき、「外部からの推薦」は最強の説得材料になります。たとえば、取引先候補の名前を検索した際、業界メディアでの紹介や、専門家からの言及、第三者の評価記事などが出てきたら、それだけで「きちんと認められている会社なんだな」という安心感が生まれます。
また、社内でプレゼンや稟議を通す際も「他サイトでも紹介されています」という事実は非常に有効です。BtoBこそ、「紹介されているという事実」が信頼の土台になるのです。
「自社で発信できないこと」を、第三者は代弁できる
真面目で謙虚な企業ほど、実力や実績を声高にアピールすることを苦手とします。
「うちなんかまだまだですから…」といった謙遜が文化になっている中小企業も少なくありません。
しかし、どれだけ優れた技術や顧客満足を誇っていても、それを誰も知らなければ、選ばれることはありません。
そんなときに有効なのが、第三者による紹介記事です。
外部のライターや媒体が客観的に企業を取材・評価することで、「こんな強みがある」「実際の現場でこう活躍している」といったリアルな実力を、自然な形で代弁してくれます。
自分で自分を褒めると白々しくなりがちですが、他者が語ることで「事実として伝わる」のです。
特に実直な企業ほど、この第三者視点を活かすことで本来の魅力が浮き彫りになります。
専門的な立場からの言葉は、信頼を生む
人は、「詳しい人が言っているなら信じよう」と無意識に判断する傾向があります。
これは「専門性バイアス」と呼ばれ、医師、研究者、職人、業界経験者など、専門家による推薦には絶大な影響力があります。
たとえば、健康食品の紹介記事で「製造元が言っている」よりも「栄養士が推薦している」と書かれている方が安心感がありますし、エステサロンの紹介でも、美容のプロがコメントを添えていれば、それだけで信頼度が増します。
同じ情報でも「誰が語っているか」で信頼性は大きく変わるのです。
そのため、専門家や実績ある第三者に語ってもらうことで、自社の価値が客観的に「保証された情報」として読まれやすくなります。
これは企業の公式SNSや広告では絶対に得られない効果です。
推薦記事は「資産」。SNS投稿との違い
SNS投稿は瞬間的な拡散力に優れていますが、数日経てば埋もれてしまう「流れるコンテンツ」です。積極的に検索をされず、流れてきたものを見るという文化です。
一方、ウェブサイトは「蓄積していくコンテンツ」です。
つまり、第三者による推薦記事は、Web上に「残る情報」であり、資産の一系統です。
SEO対策がされた外部記事は、半年後も1年後も検索され続け、安定的に露出機会を生み出します。これは、いわば「価値ある資産」のような存在です。
一度きちんと構成された推薦記事は、公式サイトとは違う立場から企業の魅力を補足し続けるメディアとして、検索流入やリピート訪問を支えてくれます。
一過性のバズではなく、長期にわたってブランド価値を底上げしてくれる──。それが推薦記事の強みです。
情報が氾濫する今だからこそ、「検索に耐える情報」「数年残る情報」を意識した発信が求められています。
自画自賛の記事は滑稽。だから第三者視点の記事が効果を発揮する
「うちはすごい」「実績が豊富」「顧客満足度No.1」──これらの言葉が、公式サイトに並んでいたとしても、読む側には「売り込み」にしか見えません。
むしろ、あまりに自信満々すぎる発信は、見る人に不信感を与えてしまうことさえあります。
人は「自分で自分をほめている人」よりも、「他人から信頼されている人」に魅力を感じやすいことは確かです。それは企業も同じです。
だからこそ、自社ではなく第三者が語る記事が必要なのです。
たとえ同じ内容であっても、語り手が変わるだけで受け取り方は大きく変わります。「あ、ちゃんと評価されているんだな」「自分の目だけじゃなかった」と納得感を持ってもらえるのです。
信頼されたいなら、自分で語るより、信じられる他人に語ってもらうほうが効果的──。これはあらゆる業界に共通する、普遍的な真理です。
つまり…
どれだけ素晴らしい商品・サービスでも、「知られていなければ、選ばれない」というのが今の時代です。
そして、人は「誰かがすすめている」「あちこちで見かける」ものに対して信頼感を持ちやすい傾向があります。
これは、あなたが発信する情報だけではなく、「第三者による推薦」をつくっていくことが大切であることを意味します。
知名度を爆上げしたい!認知度アップの対策を施したい!知名度が薄い今こそ、外部メディアで紹介される価値を見直し、「知られている状態」を一気に積み上げていきませんか?
Web上での信頼の輪は、あなたが思っているよりも、意外なところから広がっていきます。そして信頼される企業、サービスへと育っていくのです。
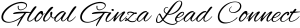

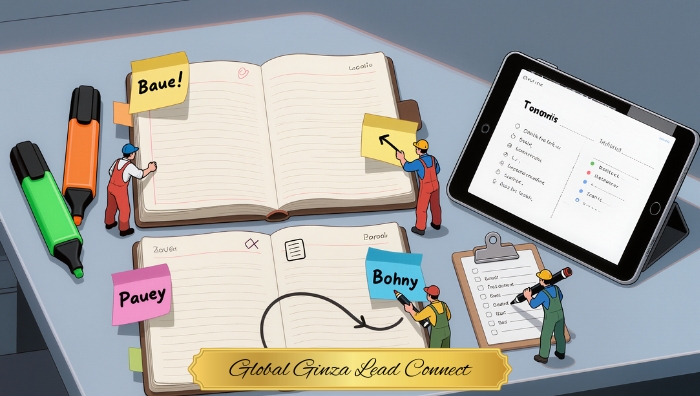
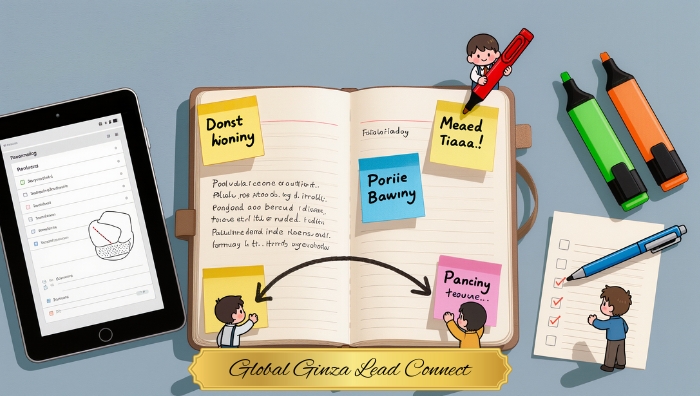
コメントをお寄せください コメントをいただけるとこのうえない喜びです♪