AIアルマゲドン、トラフィック50%減少の悪夢をどう乗り越えるのか
AI検索が奪ったクリックという習慣
数十年にわたり、インターネットの玄関口であり続けた検索という行為が、今、静かに変化の時を迎えている。この変化を「Googleの終焉」と見ている者たちもいる。
かつては当たり前だった
一部のユーザーから
- 【調べる】
- 【探す】
- 【選ぶ】
というプロセスが、AIの進化によって不要になったと思われ始めているからだ。
「質問すれば、答えが返ってくるシステム」へと検索設計が移行しつつあり、それによってグーグル検索という盤石な支配力は目に見えて低下し、AIチャットや音声ベースのリサーチが主流に入りつつあるという。
この変化は、単なるツールの入れ替えではない。情報が届く順番、読者が動く動線、ビジネスの根幹までもが再設計を迫られています。
これは第四次産業革命に匹敵するそうです
そんな中で、今この瞬間にも、訪問者を失っているウェブサイトは数えきれないほど増加している。アクセスが減り、商品が売れず、盤石だった収益の大黒柱が音もなく崩れていく。
今回は、なぜ今こんな事態が起きているのか。そして、どうすれば御社のウェブサイトは生き延びられるのか。あらゆるWeb運営者に共通する「次の選択肢」を明らかにする。
Webサイトに人が来なくなる!?AI検索時代の「検索構造設計」
目に見える数字は、小さな変化に見えるかもしれない。だが、しかし、たとえ「1%のズレ」だとしても、インターネットの根本構造を揺るがす可能性をはらんでいる。
Googleの検索市場におけるシェアは、長らく90%以上を維持していた。どの国でも、どの端末でも、検索といえばGoogle。それが世界の常識だった。
しかし、2025年。ついにその数字が89%を割った。わずか1%と思うかもしれないが、それは「Googleが圧倒的な力を誇った市場の天井」の一部が崩れ落ちたことを意味している。あなたはほんの一部が崩れただけで、Googleが強いことに変わりはないと思っているかもしれない。いや思いたいかもしれない。しかしこれは長らくエネルギー業界を支配していた「石炭」と同じ現象なのだ。石炭もこの1%から崩れ落ちたのだ。つまりこれは「革命」かもしれないということを意味する。
さらに、デスクトップ環境ではシェアが80%を切り、iPhoneの標準ブラウザ「Safari」での検索利用も22年ぶりに減少。Apple側からもAI検索との連携を示唆する発言が飛び出し、Googleの優位は確実に揺らいでいる。
原因は明確だ。検索した際に、AIが答えを「その場で返すようになったからだ」。
これまでは、検索結果に表示されたリンクをクリックして初めて情報が得られた。だが今は、AIが複数サイトの情報を先回りして調査して、独自に要約し、質問者の意図に沿った答えを返すようになったからだ。
その結果、ユーザーはリンク先、すなわちウェブサイトに行かなくなった。表示された参照元にすら飛ばず、画面上の回答だけで満足する。情報は見られているのに、サイトには訪問されない。この「情報の分断」が、いま多くのWeb運営者を直撃している。
AIは、さまざまなウェブサイトの情報を勝手に使って、それをサービスにして商売にしている。なんという「すき間ビジネス」だ。
SEO神話の崩壊と戦略再構築の必要性
かつては、「検索結果の上位に表示されること」が、成果を生む最短ルートだった。良質な記事を積み上げ、外部リンクを獲得し、アルゴリズムの傾向を読み解く。それが正攻法とされていた。
だが、そのロジックは今、根本から覆されつつある。
Googleは、AIによる回答生成を優先する方向へと舵を切った。
AI概要欄(Overviews)が検索結果の最上部に表示されることで、従来の「1位表示サイト」の位置は実質的に「二段目」以下へ押し下げられている。さらに厄介なのは、ユーザーがそのAI回答だけで満足してしまうことだ。AIが示す内容は要点が整理されており、ユーザーはわざわざ個別サイトを訪れなくても事足りてしまうと思ってしまうからだ。
結果として、「見られても訪問されない」というジレンマが発生する。SEOで上位を取ったとしても、クリックされなければ意味がありません。
この変化は、数字に表れている。ジャンルによっては、検索流入がこれまでの半分以下になり、トラフィック依存型のビジネスモデルでは致命的な打撃となっている。
情報を発信すれば人が集まる…。そんな前提は、もはや幻想に過ぎない。今必要なのは、かつての成功体験を手放し、設計そのものを塗り替える視点だ。
AIに拾われる情報と無視される情報の違い
すべてのコンテンツが、AIに等しく扱われているわけではない。情報の価値を決めているのは、もはや読者ではなく「AIの選別基準」だ。
これは、このAI検索時代において、最も重要なポイントなので、あえて再度強調したい。
すべてのコンテンツが、AIに等しく扱われているわけではありません。情報の価値を決めているのは、もはや読者ではなく「AIの選別基準」と言えるでしょう。
現在の生成AIは、信頼性のある情報源を参照し、それらを要約した上で回答を提示する仕組みを採用している。つまり、どのサイトが「回答の材料」として選ばれるかによって、生死が分かれるのだ。
では、どのような情報が拾われ、どのようなものが無視されるのか?
鍵を握るのは、構造と背景にある信頼性である。単なる主観的な意見や薄い体験談では、AIにとっての「引用に値する情報」とは見なされにくい。
逆に、客観的データ・専門的視点・具体的な一次情報に基づいたコンテンツは、参照元として選ばれやすい傾向がある。加えて、誤情報や曖昧な表現を避ける工夫も重要だ。AI側が幻覚(ハルシネーション)を抑えるために出典精査を強化している以上、「信頼できる語り方」が問われているというわけだ。
結果として、ただ記事を書けば伝わる時代は終わったと言えそうです。いま求められているのは、「AIに引用されるレベル」で情報を構築できるかどうか。その差が、流入と無視、明暗を分けている。
しかし、これは当社の見解では決して「決定打」ではないと考えます。
「見に来てもらう」から「伝えにいく」へホームページの役割を変えよ
かつては、誰かが検索し、自らの意思でサイトを訪れてくれることが前提だった。
だから、記事を更新すれば自然に人が集まり、売上につながる…。
そんな構造が成立していたのは確かだ。
だが今、検索からの流入は激減し、サイトを「発見してもらう」こと自体が難しくなっている。そこで必要なのが、ホームページや情報ページの「役割そのもの」を見直す視点だ。
つまり、自社Webサイトに対する視点を「再設計」すること。これはなにもウェブサイトを再設計し作り直せということを伝えたいわけではありません。
役目を変えるということ。
その中で、まず第一に最優先すべきは、「営業的に機能するページを用意すること」。アクセスが少なくても、見た人がすぐにサービス内容を理解し、問い合わせや購入へ進める設計が求められる。
早い話、アクセス1でも、その1人が購入や問い合せをすればいい。
これは、極端な例ではありますが、つまり、そういうことである。
そのためには、自己紹介のような形式ではなく、訪問者が求める情報を端的に提示する構成が必要だ。実績、強み、料金、申し込み方法、口コミなどを迷わず伝える。
また、検索されない時代だからこそ、自社のLINE・SNS・メールなど、外部からの導線を活用し、「見てもらいたい人に確実に届ける」仕組みも重要になる。
待っていても誰も来ない。これからは、「探してもらう」のではなく「こちらから出会いを設計する」という発想が、生き残る道を開く。
つまり、「受動的」から「能動的」へ視点を変える。これは「革命」であり、「改革」と言えましょう。
Googleに振り回されてませんか?それはもはや時代遅れ
数年おきに変わる検索アルゴリズムに一喜一憂し、表示順位の上下に右往左往。そんな運営スタイルが、そもそも持続不可能だったのかもしれません。
しかも、今は数年おきではなく、数ヶ月おきで、1年に何度もGoogleコアアップデートが行われています。これを生殺与奪はGoogleが握っているという声もあるのです。
これは、あながち否定できません。
それに加えて、言葉を選ばすに言ってしまえば、Google自身が従来型の検索構造を自ら壊しにかかっています。AIによる自動回答を最上部に据え、ユーザーの離脱を前提とした導線設計に転換し始めたからです。
かつては「努力して上位を取れば報われる」という暗黙の約束がありました。良質な記事を出し続け、SEO対策を徹底すれば、流入と収益が見込めた。だが今は大きく異なります。GoogleがAI時代に対応するため、自らその「報酬システム」を廃止し始めたと言えば過言でしょうか…。
いや、そうは思いません。
いま、さまざまなウェブマスター(ウェブ責任者)の嘆きの声が聞こえるからです。
つまり、SEOを軸に構築されたビジネスモデルは、すでに大きな打撃を受けているわけです。アクセスを頼りにしていた企業の中には、売上の急落や事業撤退に追い込まれた例もあります。この流れはさらに加速しそうです…。
検索エンジンに運命を預けていては、時代の変化に対応できません。そろそろ「表示されるかどうか」で一喜一憂する運営そのものを見直すべき時が来ているというわけです。情報を届ける手段は、すでに検索だけではありません。「自分で情報を届けに行く設計」「自分でユーザーと関係性を育てる設計」こそが、これからの軸になることは間違いないのではないでしょうか。
しかし、依然としてウェブサイトが無用になるわけではありません。実はその逆でさらに重要度は増しているのです。
読みたくなる文章に共通する「文字温度」の正体
読まれる文章と、通り過ぎられる文章。その差は、情報量でも構成力でもない。「ここにしかない温度」があるかどうかです。
AIが答えを即座に返す時代、やがて人は「正しい情報」だけではもの足りないと感じはじめるでしょう。「それを誰が語っているか」も重要になってきます。そして「どのような体験から生まれた言葉か」に、より深く反応するようになっています。つまり感情であり魂と言っても過言ではありません。これは現代版の「言霊」と言えるかもしれません。
もはや、青いリンクを片っ端から開いて正解を探す時代ではないというわけです。効率的な要約が手に入る今、読み手が求めているのは「納得できる共感」とその「根拠」であり、「人の手触りから生まれた言葉」というわけです。
一方、感情が感じられない文章、誰が書いても同じような記事、一次情報が欠落した内容は、読まれることなくAIにも見過ごされていくでしょう。
たとえ検索で表示されなくても、たった一人の心に届けば、その文章には価値があると言えましょう。読者は情報だけではなく、「言葉の背景」に触れたときに、心が動きます。
だからこそ、体験に基づいた語り方、独自の視点、他では見つからない切り口こそが、読みたくなる文章の「熱源」となりそうです。それはAIにも再現できない、人間だけの強みと言えるでしょう。
つまりAIに書けない文章を書く必要があるわけです。
これからの運営者に求められる実務修正点
状況の変化を理解するだけでは足りない。運営の現場では、具体的に何を変えるかが問われている。以下は、今後1年間で必須となりそうな修正項目を挙げてみる。
- SEO流入に依存せず、LPや営業導線で機能する構成も視野に入れる。
- 古い記事の大半はアクセスに貢献しない確率が高い、信頼性の低下にもつながる。情報の正確性、設計を随時最新の内容に修正する。
- SNS、LINE、メール、名刺など、自ら届けにいく手段を明確に持つ。
- 他ウェブサイトと同じ情報ではAIにも人間にも選ばれない。体験談、顧客の声、現場の声を素材化する。
- 情報提供だけで終わらせず、次のアクションへの誘導を明確にする。
- Googleアナリティクス、サーチコンソールを活用し、無駄なページや離脱ポイントを見つける。
躍進するメディアの設計図とは何か?
これまで私たちは、「情報を持つ者が勝つ」という時代を生きてきた。だけど今、情報の「届け方」そのものが塗り替えられつつあります。
つまり「情報弱者」が少数になるというわけです。
それは情弱ビジネスが成り立たないことを意味します。
今後5年、Webのエコシステムは根本的に変わるでしょう。アクセスを基盤にしたモデルは崩れ、「どう見つけてもらうか」ではなく「どう届けるか」が主戦場になります。だからこそ必要なのは「シェアしたくなる記事」「読まれる動線づくり」「信頼される構成」です。
たとえ検索に表示されなくても、会社名や商品名で指名検索されたり、または他者に紹介されたり、参考にされたり資料として使われるウェブコンテンツをつくることです。それこそが「生き残るウェブサイト」の設計図と言えるでしょう。
まとめ・変化を嘆いても何も変わらない。思考を切り替えて設計し直すアクションを起こす
だからこそ!
当社グローバル銀座リードコネクトが役に立つことができます!
検索が機能しなくなったわけではありません。
とはいえ、御社のウェブサイトの情報が「検索」によって届きにくくなったのは否定できません。しかし恐れても何も変わりません。
ただ、届け方のルールが変わった…。それだけのことなのです。
AIが主導する時代において、求められているのは「正しい情報」は元より、それに加えて「確かな意図」と「設計された体験」を提供することです。
大切なことは、ユーザ—に対して「根拠」と「納得」を与えること。
グローバル銀座リードコネクトは、その「根拠」と「納得」を設計するお手伝いをさせていただきます!
訪れてほしい相手に、何をどう伝えたいのか。クリックに頼らず、信頼と反応をどう生み出すのか。
その問いに向き合い、ページの役割、文章の意味、導線のすべてを再構築できるかどうか。それこそが、これからの時代に生き残るウェブサイトと、埋もれていくウェブサイトを分ける境界線となります。
グローバル銀座リードコネクトにお任せください!
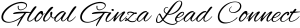

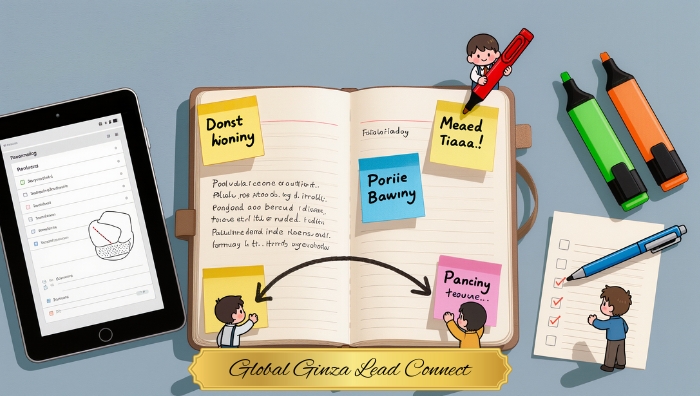

コメントをお寄せください コメントをいただけるとこのうえない喜びです♪